笹川平和財団日米グループとは?
笹川平和財団日米グループでは、アメリカの政治社会、国際政治環境が大きく変化しているなかで、強固な日米関係が地域の安定と繁栄につながるという認識のもと戦略的人物交流を通した多面的で緊密なネットワークの構築、外交・安全保障問題を中心とした政策研究・共同研究の推進、日米両国の若手世代の専門家育成、情報発信の強化など、様々なプロジェクトを実施しています。
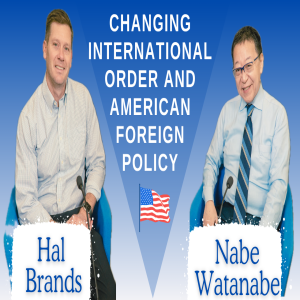
Monday Jun 30, 2025
Monday Jun 30, 2025
Monday Jun 30, 2025
In this episode, we invited two distinguished experts Dr. Hal Brands and Mr. Tsuneo (Nabe) Watanabe to hold a discussion, "Changing International Order and American Foreign Policy."
(1) Recorded on: Thursday, May 29, 2025 (JST)
(2) Discussants:
Dr. Hal Brands (Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University)
Mr. Tsuneo (Nabe) Watanabe (Senior Fellow, Sasakawa Peace Foundation)
*Disclaimer: The views and opinions expressed in this discussion are those of the speakers and do not represent the views of the Sasakawa Peace Foundation or the institutions to which the participants belong

Tuesday Nov 19, 2024
Tuesday Nov 19, 2024
Tuesday Nov 19, 2024
<テーマ:2024米国大統領選挙:トランプ2.0 -今後の米国外交政策への影響>
本エピソードでは、11月5日の大統領選挙でドナルド・トランプ前大統領が次期大統領に確定したことを受け、2024年以降の米国外交政策への影響について、「アメリカ現状モニター」研究会のメンバーであるお二人に大統領選挙の総括、そしてウクライナ、中東、中国など広く外交政策への影響についてお話しいただきました。
※このエピソードの議論の内容も含むお二人の最新論考が、近日中に日米関係インサイト「アメリカ現状モニター」から公開予定です。
(1)ゲスト:森聡氏(慶應義塾大学教授)
渡部恒雄氏(笹川平和財団上席フェロー)
(2)収録日:2024年11月14日(木)
(3)使用言語:日本語
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<森 聡 氏の略歴>
慶應義塾大学法学部教授
1995年3月京都大学法学部卒。同大学大学院法学研究科及び米コロンビア大学ロースクール修士課程修了。外務公務員採用Ⅰ種試験で外務省入省。同省退職後、2007年に東京大学大学院法学政治学研究科にて博士(法学)。2008年より法政大学法学部准教授、2010年から2022年3月まで同教授。この間、米プリンストン大学(2014~2015年)及びジョージワシントン大学(2013年~2015年)で客員研究員。2022年4月より現職。現在の研究テーマは、米中関係・日米関係を含むアメリカのアジア戦略、先端技術と国防イノベーション、冷戦期アメリカの戦略史。
2018年より中曽根平和研究所上席研究員。内閣官房国家安全保障局政策参与・シニアフェロー(2016年~2019年)。2020年より防衛省新防衛政策懇談会委員。2022年に国家安全保障局が実施した防衛三文書見直しに関する専門家ヒアリングに招集。2023年3月より慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート・戦略構想センター副センター長。
<渡部 恒雄 氏の略歴>
笹川平和財団 安全保障研究グループ上席フェロー
専門:米国の外交・安全保障政策、アジアの安全保障
1963年福島県に生まれる。1988年、東北大学歯学部卒業、歯科医師となるが、社会科学への情熱を捨てきれず米国留学。1995年ニューヨークのニュースクール大学で政治学修士課程修了。同年、ワシントンDCのCSIS(戦略国際問題研究所)に入所。客員研究員、研究員、主任研究員を経て2003年3月より上級研究員として、日本の政党政治、外交安保政策、日米関係およびアジアの安全保障を研究。2005年4月に日本に帰国。以来CSISでは非常勤研究員を務める。三井物産戦略研究所主任研究員を経て、2009年4月から2016年8月まで東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員。10月に笹川平和財団に特任研究員として移籍。2017年10月より上席研究員となり、2024年4月より現職。外交・安全保障政策、日米関係、米国の政策分析に携わる。
2007年から2010年まで報道番組「サンデープロジェクト」(テレビ朝日系)のコメンテーターを務め、現在、「激論!クロスファイア」(BS朝日)、「深層ニュース」(BS日テレ)、「日経ニュースプラス9」(BSテレ東)、「報道1930」(BS-TBS)、「プライムニュース」(BSフジ)などで国際問題を解説。2010年5月から2011年3月まで外務省発行誌「外交」の編集委員を務め、現在、防衛省の防衛施設中央審議会委員。
著書に「国際安全保障がわかるブックガイド」(共著、2024年、慶應義塾大学出版会)、「NATO(北大西洋条約機構)を知るための71章」(共著、2023年、明石書店)、「デジタル国家ウクライナにロシアは勝利するか?」(共著、2022年 日経BP)、「防衛外交とは何か―平時における軍事力の役割」(共編著、2021年 勁草書房)、「2021年以後の世界秩序―国際情勢を読む20のアングル」(2020年 新潮新書)、「いまのアメリカがわかる本・最新版」(2013年 三笠書房)、「二〇二五年米中逆転―歴史が教える米中関係の真実」(2011年 PHP研究所)等。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
🔹関連ポッドキャスト:
【渡部恒雄の視点】2024米国大統領選挙:民主党全国大会を終えて
🔹「アメリカ現状モニター」※近日中にこのエピソードでの議論を踏またお二人の論考も公開予定です。
🔹日米グループの情報発信サイト「日米関係インサイト」
🔹SPF 国際情報ネットワーク分析IINA(渡部上席フェローがチーフ・エディターを務めています)
🔹日米グループXアカウント:@SPFJapanUS

Wednesday Sep 04, 2024
Wednesday Sep 04, 2024
Wednesday Sep 04, 2024
<テーマ:2024米国大統領選挙:民主党全国大会を終えて>
本エピソードでは、笹川平和財団安全保障研究グループの渡部恒雄上席フェローに、民主党党大会を終え11月5日の投票日まで約2か月と迫った米国大統領選挙の現状について、話を伺いました。
(1)ゲスト:渡部恒雄氏(笹川平和財団上席フェロー)
(2)収録日:2024年8月23日(金)
(3)使用言語:日本語
(4)進行:村田綾(笹川平和財団日米グループ グループ長)
(5)0:00~4:00 導入・渡部氏の紹介
04:00 ~ 渡部上席フェローの話スタート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<渡部 恒雄 氏の略歴>
笹川平和財団 安全保障研究グループ上席フェロー
専門:米国の外交・安全保障政策、アジアの安全保障
1963年福島県に生まれる。1988年、東北大学歯学部卒業、歯科医師となるが、社会科学への情熱を捨てきれず米国留学。1995年ニューヨークのニュースクール大学で政治学修士課程修了。同年、ワシントンDCのCSIS(戦略国際問題研究所)に入所。客員研究員、研究員、主任研究員を経て2003年3月より上級研究員として、日本の政党政治、外交安保政策、日米関係およびアジアの安全保障を研究。2005年4月に日本に帰国。以来CSISでは非常勤研究員を務める。三井物産戦略研究所主任研究員を経て、2009年4月から2016年8月まで東京財団政策研究ディレクター兼上席研究員。10月に笹川平和財団に特任研究員として移籍。2017年10月より上席研究員となり、2024年4月より現職。外交・安全保障政策、日米関係、米国の政策分析に携わる。 2007年から2010年まで報道番組「サンデープロジェクト」(テレビ朝日系)のコメンテーターを務め、現在、「激論!クロスファイア」(BS朝日)、「深層ニュース」(BS日テレ)、「日経ニュースプラス9」(BSテレ東)、「報道1930」(BS-TBS)、「プライムニュース」(BSフジ)などで国際問題を解説。2010年5月から2011年3月まで外務省発行誌「外交」の編集委員を務め、現在、防衛省の防衛施設中央審議会委員。 著書に「国際安全保障がわかるブックガイド」(共著、2024年、慶應義塾大学出版会)、「NATO(北大西洋条約機構)を知るための71章」(共著、2023年、明石書店)、「デジタル国家ウクライナにロシアは勝利するか?」(共著、2022年 日経BP)、「防衛外交とは何か―平時における軍事力の役割」(共編著、2021年 勁草書房)、「2021年以後の世界秩序―国際情勢を読む20のアングル」(2020年 新潮新書)、「いまのアメリカがわかる本・最新版」(2013年 三笠書房)、「二〇二五年米中逆転―歴史が教える米中関係の真実」(2011年 PHP研究所)等。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
🔹日米グループの情報発信サイト「日米関係インサイト」
【渡部恒雄の視点】岸田総理の米国公式訪問-日米首脳共同声明
🔹SPF 国際情報ネットワーク分析IINA(渡部上席フェローがチーフ・エディターを務めています)
🔹日米グループXアカウント:@SPFJapanUS

Friday Jan 19, 2024
Friday Jan 19, 2024
In this episode, we invited two distinguished experts Dr. Hal Brands and Dr. Zack Cooper to hold a discussion, "Challenges facing the U.S. and Japan in 2024: Russia-Ukraine War, Middle East, China, and the U.S. Presidential Election." Since the beginning of the Biden administration, the U.S. has faced three regional security issues: Russia's invasion of Ukraine, the war between Israel and Hamas, and competiton with China. In addition, the U.S. presidential election is coming up in 2024 amidst these circumstances. How does this destabilizing security environment and dynamics of domestic politics affect the U.S. strategy, which wants to focus on strategic competition with China? And what are the roles and challenges of the Japan-U.S. alliance under this circumstance? In this episode, Dr. Brands and Dr. Cooper discuss a wide range of issues, including the current international order and the U.S.-China relations, the impact of the U.S. domestic politics, and their implications for the Japan-U.S. alliance and the security of the Indo-Pacific region, such as the South China Sea and Taiwan Strait. You can listen to the podcast below.
Details of the podcast👇
https://www.spf.org/jpus-insights/ideas-and-analyses-en/20240119_01.html
(1) Recorded on: Wednesday, January 17, 2024 (JST)
(2) Discussants:
Dr. Hal Brands (Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University)
Dr. Zack Cooper (Senior Fellow, American Enterprise Institute)
*Disclaimer: The views and opinions expressed in this discussion are those of the speakers and do not represent the views of the Sasakawa Peace Foundation or the institutions to which the participants belong

Monday Nov 13, 2023
Monday Nov 13, 2023
Like-Minded Allies? Indo-Pacific Partners’ Views on Possible Changes in the U.S. Relationship with Taiwan
*This episode is originally from the webinar "Like-Minded Allies? Indo-Pacific Partners’ Views on Possible Changes in the U.S. Relationship with Taiwan" held on October 5, 2023.
Details of the seminar👇
https://www.spf.org/jpus-insights/ideas-and-analyses-en/20230926_01.html
This episode featured a report, "Like-Minded Allies? Indo-Pacific Partners' Views on Possible Changes in the U.S.-Japan Relations," which was the result of a study conducted by the RAND in cooperation with the Japan-U.S. Program. In this episode, three experts from the RAND, the core authors of the report, gave a background and overview of the report, such as the reason why they focus on allies rather than US policy on Taiwan itself, the perceptions and reactions of each ally, Japan, South Korea, and the Philippines. Afterwards, two Japanese experts as commentators joined the discussion and they discussed various issues including the implications of the research in the view of China and Taiwan, and the influence of domestic politics in the U.S. and each ally.
(1) Recorded on: Thursday, October 5, 2023 (JST)(2) Panelists:
Dr. Jeffrey W. Hornung(Senior Political Scientist, RAND Corporation)
Dr. Miranda Priebe (Director, Center for Analysis of U.S. Grand Strategy; Senior Political Scientist, RAND Corporation)
Dr. Bryan Rooney (Political Scientist, RAND Corporation)
Dr. Saya Kiba (Associate Professor, Department of International Relations, Kobe City University of Foreign Studies)
Mr. Tsuneo Watanabe (Senior Fellow, Security Studies Program, Sasakawa Peace Foundation)
*Disclaimer: The views and opinions expressed in this discussion are those of the speakers and do not represent the views of the Sasakawa Peace Foundation or the institutions to which the participants belong.
The original video of this episode is available on YouTube 👇
https://www.youtube.com/watch?v=WQBd3MU4XfE

Monday Nov 13, 2023
Monday Nov 13, 2023
*This episode is originally from the public seminar "The Future of U.S.-China Rivalry and Changes in the International Security Environment" held on August 22, 2023.
Details of the seminar👇
https://www.spf.org/jpus-insights/ideas-and-analyses-en/20230908.html
In this episode, we hosted Dr. Hal Brands (Professor, Johns Hopkins University, SAIS) and Dr. Zack Cooper (Senior Fellow, American Enterprise Institute).
Dr. Hal Brands is an expert on American strategy and Cold War history, and in recent years, he has written numerous articles and books on the U.S.-China rivalry and U.S. foreign policies. His recent book, Danger Zone: The Coming Conflict with China, was also published in Japanese and has received a lot of attention in Japan. Dr. Zack Cooper is also an expert on U.S. defense policy in Asia, alliances, and U.S.-China strategic competition, and has written numerous reports and articles and appeared on podcasts.
In this episode, Dr. Brands gave a speech based on his argument in Danger Zone; why China now faces peak-out, why this situation could increase the risk of US-China conflict, and what the US needs to do to deter China. Afterwards, Dr. Satoru Mori (Keio University) and Dr. Cooper joined a discussion with Dr. Brands, and exchanged their views and thoughs on a wide range of issues, including the impact of next year's election in Taiwan on China's policy, the role of nuclear weapons in Taiwan's contingency, and the prospect of strategic ambiguity.
(1) Recorded on: Tuesday, August 22, 2023 (JST)(2) Speakers:
Speaker: Dr. Hal Brands (Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University)
Commentator: Dr. Zack Cooper (Senior Fellow, American Enterprise Institute)
Moderator: Dr. Satoru Mori (Professor, Faculty of Law, Keio University)
(3) Languages: English and Japanese
*Disclaimer: The views and opinions expressed in this discussion are those of the speakers and do not represent the views of the Sasakawa Peace Foundation or the institutions to which the participants belong.
The original video of this episode is available on YouTube 👇
https://www.youtube.com/watch?v=RG_iiPTlEEo

Wednesday Apr 26, 2023
Wednesday Apr 26, 2023
Wednesday Apr 26, 2023
Two Nuclear Peer Problem: Implications for U.S. Nuclear Deterrence Strategy
In this episode, we welcome two distinguished experts; Dr. Brad Roberts and Mr. Sugio Takahashi. Dr. Roberts and Mr. Takahashi were involved in the publication of a report by CGSR entitled "China's Emergence as a Second Nuclear Peer: Implications for U.S. Nuclear Deterrence Strategy". Based on this report, they discuss a wide range of issues surrounding the nuclear weapons, including extended deterrence, hedging, counter force capability, arms controle, and command planning of Japan-US Alliance.
(1) Recorded on: Tuesday, April 18, 2023 (JST)(2) Discussants:
Dr. Brad Roberts (Director of the Center for Global Security Research at Lawrence Livermore National Laboratory)
Mr. Sugio Takahashi (Head of the Defense Policy Division of the Policy Studies Department at Japan’s National Institute for Defense Studies)
*Disclaimer: The views and opinions expressed in this discussion are those of the speakers and do not represent the views of the Sasakawa Peace Foundation or the institutions to which the participants belong.
The original video of this episode is available on YouTube 👇
https://www.youtube.com/watch?v=ayem0aWGNhM

Friday Mar 24, 2023
Friday Mar 24, 2023
Friday Mar 24, 2023
2023年の米国:対中政策議論の現状
本エピソードでは、「アメリカ外交政策の中長期的展望と日本の課題」プロジェクトより松田康博氏(東京大学東洋文化研究所教授)をゲストにお招きし、「2023年の米国:対中政策議論の現状」と題する対談を実施いたしました。中国、台湾をめぐっては、ナンシー・ペロシ下院議長の訪台、半導体輸出規制、気球問題など、常に米国における議論の中心となっています。本対談では、モデレーターに秋田浩之氏(日本経済新聞社コメンテーター)をお迎えし、現在のアメリカにおける中国、台湾海峡をめぐる議論はどのように展開されているのか、松田氏がアメリカで直接現地調査をされて得られた知見も踏まえ、お話しいただきました。
(1)収録日:2023年3月9日(木)(2)対談者: モデレーター:秋田浩之氏(日本経済新聞社コメンテーター) スピーカー: 松田康博氏(東京大学東洋文化研究所教授)(3)使用言語:日本語
本エピソードのオリジナル動画はYouTubeにてご覧いただけます👇
https://www.youtube.com/watch?v=FndCyXCWW4U
調査・研究プロジェクトページはこちら👇
https://www.spf.org/jpus-insights/spf-future-japanus/movie20230310.html
笹川平和財団日米グループでは、アメリカの政治社会、国際政治環境が大きく変化しているなかで、強固な日米関係が地域の安定と繁栄につながるという認識のもと戦略的人物交流を通した多面的で緊密なネットワークの構築、外交・安全保障問題を中心とした政策研究・共同研究の推進、日米両国の若手世代の専門家育成、情報発信の強化など、様々なプロジェクトを実施しています。